元素漢字の未来(最終回)
ここまで、元素名を表記する古今の漢字について、中国、日本、ときには韓国、ベトナムを眺めてきた。辞書に載る字が定まるまでに、さまざまな試行錯誤が繰り返され、人々によって淘汰され、選ばれてきた漢字が非常に多いことに驚かれたこ[…]
もっと読む
ここまで、元素名を表記する古今の漢字について、中国、日本、ときには韓国、ベトナムを眺めてきた。辞書に載る字が定まるまでに、さまざまな試行錯誤が繰り返され、人々によって淘汰され、選ばれてきた漢字が非常に多いことに驚かれたこ[…]
もっと読む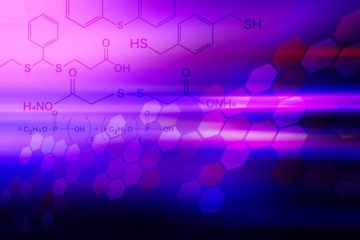

ここまで、概説から始まり、個々の元素として、ウラン、マグネシウム、フッ素、酸素に焦点を当てて、それぞれの元素の漢字の成り立ちを追ってきた。試作品のような字を含めて、たくさんの漢字を眺めてきた。 歴史的な変遷のパターンは、[…]
もっと読む
日清戦争(1894-1895)の後、中国では、日本の近代科学を取り入れようとする動きが各界で盛んとなった。1900年に章炳麟が、日本から伝わった「酸素」を用いた。1906年に刊行された中国語の化学書にも、「酸素」が使用さ[…]
もっと読む
前回述べたように酸素の「酸」は一種の誤訳であるのに、漢字の画数が多くて書くのに面倒ではなかっただろうか。他の国々の状況を見ていこう。 酸素のことをお隣の韓国では、ハングルで、 산소 と表記するのが普通である。「サンソ」と[…]
もっと読む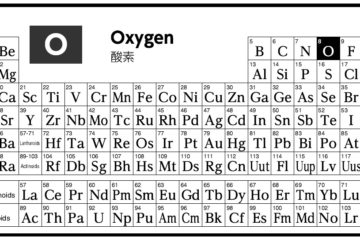
ここまで金属元素を表す金偏の字、非金属元素を表す「气」構えの字に焦点を当ててきた。今回は、前回の「フッ素」と同じく常温・常圧時に気体の元素であるが、視点を変えて普通の漢字を使った「酸素」について見ていこう。 こんな見慣れ[…]
もっと読む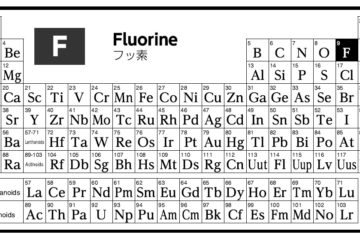
前回、フッ素が「弗」という漢字を江戸時代に当て字として獲得していたこと、そして明治時代にそこから「弗素」という熟語が形成されたことを紹介した。 明治という時代は、その前の江戸時代に負けず劣らず多様な気鋭が現れ、独自の主張[…]
もっと読む
ここまで「ウラン」「マグネシウム」と、金偏の漢字について詳しく紹介してきた。 今回は、金偏ではない元素の漢字を紹介し、その歴史と現状について説明をしたい。 フッ素(F)は、英語(IUPAC名)がFluorine(フローリ[…]
もっと読む